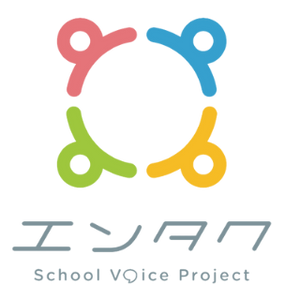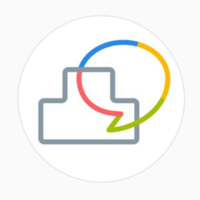\ School Voice Project presents /
学校教育をめぐる公開対話会 vol.5
〜 今回のゲストは渡邊洋次郎さん〜
「学校教育をめぐる公開対話会」とは??
いま、学校教育は、《変わり目》にあります。
全国の教職員らによるネットワークである私たち School Voice Projectは、
現場の思い・声を大事にしながらも、多様な人たちの問題意識や課題感、ビジョンに耳を傾け、対話を通して学校教育の未来を描いていこうとしています。
この企画は、(だいたい)毎月ゲストを招いて、学校教育をめぐるさまざまなテーマについて、ホスト役の現職教職員と対話していただき、その内容を参加者の方にもお聞きいただくというものです。
学校で働く人たちはもちろん、教育に関心のある多様な立場の人たちにご参加いただくことで、学校がもっとよくなっていくために不可欠な「対話の輪」が広がっていくキッカケになればと願っています。
イベント概要
●日 時:7月13日(日)20:00-21:15
●場 所:オンライン(zoom)
※お申込後、当日使用するURLが表示されます。
●内 容:
20:00 オープニング
20:05 ゲストの講和(チャットにて感想や質問受け付けます)
20:30 ゲストとの鼎談
21:00 質疑応答
※全ての質問にはお答えできない場合もあります。
21:15 クロージング
●参加費:一般 1,200円
※School Voice Projectのオンラインコミュニティ「エンタク」のメンバーは無料
(本ページよりお申込みください)
【今回、公開対話に参加する人】
●Guest:
渡邊洋次郎さん
リカバリハウスいちご(依存用回復支援施設)職員/介護福祉士
中学の頃に薬物中毒になり、4度の鑑別所入所を経て、16歳の終わりから18歳になるまでの1年間を中等長期少年院で過ごす。 20歳から30歳までの10年間で計48回の精神科病院入院。30歳から3年間の刑務所服役。 出所後から酒や薬が止まり16年が経過している。 自助グループのミーティングへの参加や就労支援を経て2018年から現職。
著作 :『下手くそやけどなんとか生きてるねん』(現代書館2019) 『弱さでつながり社会を変える』(現代書館2023)
●現職教職員:
豊田哲雄さん
小学校教員/NPO法人School Voice Project 理事 大阪府の公立小学校で、子どもの権利を大切にした学級づくりに取り組んでいる。自由進度学習やサークル対話、探究などの実践を通して、子ども一人ひとりの多様な在り方が尊重される場を模索してきた。近年は「アジール」や「ケア」の概念を手がかりに、自身の教育実践を再解釈しながら、言語化・記録する試みを続けている。
小谷綾子さん
NPO法人School Voice Project 理事/社会福祉士/SSW/子どもソーシャルワーカー
大学ではソーシャルワークと心理学を専攻。卒業後は、障害者自立生活センターの職員として活動。日本だけではなくアジア・中南米地域の支援も行う。センターでの活動の中で、子ども時代のキャッチアップの必要性を感じ、現職へ。 現在は、発達障害、学校環境、不登校、子どもへの養育不安、子どもの不適切行動、虐待、などの相談を受け、学校の外と中から子どものセーフティーネットに対して、子どもの権利を軸としたソーシャルワークの視点で働きかけている。
【今回の対話テーマ】
『問題と呼ばれる行動の裏側にあるもの。物質依存症の自助グループの在り方から考える真の主体性とは?』
渡邊洋次郎さんは、ご自身の幼少期の満たされなさからアルコールや薬物乱用を繰り返し、少年院、少年刑務所、精神科入院などを経て刑務所へ入り、現在は、最後に刑務所から出てきて物質に頼らない毎日を積み重ねる生活を送っています。
今、物質に頼らずに生活できるのは「自助グループの中で、どこの誰でもない自分がどこの誰でもない人と自身の経験を分かち合い、その上でありのままの自分でいいと認めてもらえたからこそ、自分は他の誰かにならなくてもいいと思えた経験がある」と言います。
自助グループでは「アルコールをやめることを焦点化するのではなく、アルコールを飲む自由があるからその先の飲まない選択がある」そうで「ルールに縛られるのではなく、自分ごととしてアルコールを飲まない選択ができている」と。
そして、なぜそのような状況になっていったのかを振り返った時に「子どものときから足りなかったのは対話。もっと対話をしてほしかった」とおっしゃっています。
問題と呼ばれる行動の裏にあった「さみしい気持ち」を対話を通して消化できていたら、社会のルールを自分ごととして受け入れることができ、他者から注目を集めるために問題と呼ばれる行動をしなくても済んだかもしれない、と。
学校では「主体的な選択」「主体的なあり方」を求められる今。
主体的に選び進んでいくための土台には何が必要なのか…
幼少期、洋次郎少年が学校内外での問題と呼ばれる行動の裏で感じていたことをヒントに、現職教員とソーシャルワーカーと一緒に「主体的に考え生きるために必要なこと」を考えてみたいと思います。
【主催】
NPO法人School Voice Project / スクール・ボイス・プロジェクト
「学校現場の声を見える化し、対話の文化をつくる」をミッションに、100名を越える現職・元教職員メンバーの参画によってスタート。一人ひとりの教職員が日々働きながら感じ考えていること=「学校現場の声」を見える化し、課題解決へとつなげるための組みとして、WEBアンケートサイト「フキダシ」・WEBメディア「メガホン」・オンラインコミュニティ「エンタク」の運営、さらに政策提言・ロビイングにも取り組んでいます。
[ ホームページ ]https://school-voice-pj.org
[ フキダシ ]https://fukidashi.school-voice-pj.org
[ メガホン ]https://megaphone.school-voice-pj.org
[ エンタク ]https://entaku.school-voice-pj.org/about
[ F B ]https://www.facebook.com/schoolvoice.project
[ X ]https://twitter.com/schoolvoice_pj
[ Instagram ]https://www.instagram.com/schoolvoice.project
[ 連絡先メール ]info@school-voice-pj.org