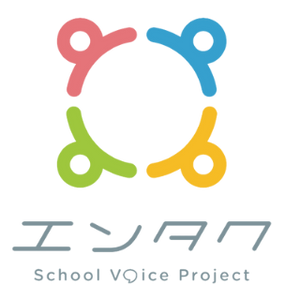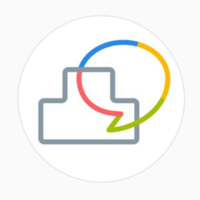インクルーシブな学びの場(がっこう)をつくるには??
学校は、子どもたちがしあわせに学び、過ごせる場であってほしい。
一人ひとりの声が大切にされ、みんなが居場所を感じられるところであってほしい。
教師も、保護者も、地域の人も。きっと多くの大人がそう願っているはずです。
ですが今、日本の学校は不登校児童生徒数が30万人に迫っていることに象徴されるように、一定数の子どもたちにとって「楽しい」よりも「つらい」場所になってしまっている現状があります。
多様な背景、特性、個性を持つ子どもたちを(結果的に)包摂できていない・排除していると言わざるを得ない状況があるとしたら、学校はここからどんなふうに変わっていけばいいのでしょうか。できれば、上から押し付けられるのではなく、【ボトムアップで、内側から】変わっていけるといいなと、私たちは考えています。
この日は、学校を「子どもも大人もしあわせな場所」「民主的でインクルーシブな場所」にしたいと願う人たちで集い、学校教育がこれからどうなっていけばいいのか、そのために一人ひとりにできることはなんなのかを、一緒に考えたいと思います。
ぜひご参加ください!
イベント概要
●日時:7/21(日)13:00-16:00
●会場: ベイシズ福岡・博多駅前貸会議室
・ 〒8120013 福岡県 福岡市博多区 博多駅東 1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前 3F
・マップ:
●定員:25人
●参加費:一般 1500円 / エンタクメンバー 500円
●共催:
NPO法人School Voice Project / CAN!P / 未来の風プロジェクト
イベント内容
●前半:主催メンバー3名からのプレゼンテーション
武田緑
学校における【DE&I(多様性・公正・包摂)】をテーマに、研修・講演・執筆、ワークショップやイベントの企画運営、学校現場や教職員への伴走サポート、教育運動づくり等に取り組んでいる。研修は、全国の学校や教育委員会、教育研究団体などでの実績多数。朝日新聞デジタル「コメントプラス」のコメンテーター、学習スタイル診断(Self-Portrait™)認定コーチでもある。 / 著書『読んで旅する、日本と世界の色とりどりの教育』(教育開発研究所)
フリーランスとしての活動のほか、学校DE&Iの実現のためには現場のエンパワメントが必要との思いから、全国の教職員らと共にNPO法人 School Voice Projectを立ち上げ、現在は理事兼事務局長として活動に従事している。
《当日はこんなことを話す予定!》
・多様性を受けとめる学校づくりのために、変えたい学校のアタリマエ
1. 形式的平等→公正へ
2. 個人モデル発想→社会モデル発想へ
3. 大人主導→こども参加へ
長崎裕也
認定NPO法人Teach for Japanのフェローとして福岡県内の公立小学校に赴任。学級担任として「子どもたちとともに心を動かす」を合言葉にさまざまな実践を行った。NPO法人School Voice Project が実施する「#学校にYogiboを置いたら」実証実験にも参加。
その後、民間で探究学習塾やアフタースクールを運営するCAN!Pへと転職。現在は、来年春開校予定のCAN!Pオルタナティブスクールの構想設計に取り組んでいる。
《当日はこんなことを話す予定!》
・フィンランドの学校で感じたこと
・公立小学校で感じたこと
・CAN!Pとは
・民間企業にいながら教育の在り方について真剣に向き合う
◎CAN!Pオルタナティブスクールで実現したい学びの場
・民間企業が守る教育の場
#元公立小学校教員 #フィンランド #CAN!P #民間企業 #Teach for Japan
#yogibo #学校の居心地 #探究
西祐樹
平成23年より福岡春日市教育委員会事務局に7年間在籍し、コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動の推進に関わる中で、学校運営の在り方、学校と地域・教育委員会との関係性、対話の場づくり、子供に必要な学びとは何なのかなどについて深く考えるようになる。また、教育委員会改革や近隣大学との連携、学校事務職員の経営参画等についても関わってきている。平成30年より文部科学省初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付に専門職として着任し、コミュニティ・スクールの全国普及に携わることに。同年10月の組織再編後は総合教育政策局地域学習推進課に籍を移し、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を担当、令和2年には課内異動により、公民館、社会教育士も担当する。令和3年4月より春日市に戻り(財政課)、文部科学省CSマイスターとして新たな活動をスタートした。そして令和6年4月より議会事務局へ。
《当日はこんなことを話す予定!》
・コミュニティ・スクールが、子供から大人まで、対話、学び、つながりの価値に気付くきっかけとなり、ジブンゴトとして行動することにつながること
・コミュニティ・スクールの仕組みを使って、これからの学校のあり方を民主的に変えていきたい
●後半:参加者みんなでじっくり対話
前半の話題提供を踏まえて、「インクルーシブな学びの場をつくるには?」をテーマに、参加者みんなで「学校教育がこれからどうなっていけばいいのか?」「そのために一人ひとりにできることは?」について考え合います。
※ワールドカフェという手法でメンバーチェンジをしながら少人数で話し合います。