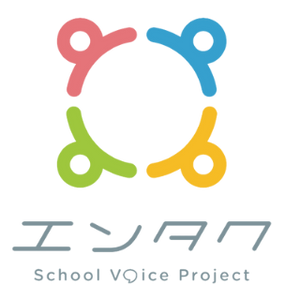@みどり@運営事務局 と @なお さんでFacebook上で「勅使河原さんの本の話がしたいねー」となり、せっかくなのでエンタクでブッククラブにしてみました。
エンタクメンバーの皆さんでも読んでいる方は多そうですね!
また、今回は外部の方にもオープンにしてみました。
『能力の生きづらさをほぐす』『働くということ』をもとに、ぜひたくさんおしゃべりしましょう!
テーマ本の紹介
📗 能力の生きづらさをほぐす
【発売たちまち重版!】
生きる力、リーダーシップ力、コミュ力…
◯◯力が、私たちを苦しめる。
組織の専門家が命をかけて探究した、他者と生きる知恵。
前職では「使えない」私が、現職では「優秀」に。
それって、本当に私の「能力」なの?
移ろいがちな他人の評価が、生きづらさを生み出す能力社会。
ガン闘病中の著者が、そのカラクリを教育社会学と組織開発の視点でときほぐし、他者とより良く生きるあり方を模索する。
――――――――――――――――――――――――
職場や学校、家庭で抱えるモヤモヤを
なかったことにしたくないすべての人へ
「行きすぎた能力社会じゃ、幼い子どもを残して死にきれない!」
ガン闘病中の著者が贈る、まさかのストーリー。
――ときは、2037年。急降下した
上司の評価で病める息子を救うため、
死んだはずの母さんがやってきた!?
「人事部が客観性の根拠として、人材開発業界を頼っているわけだね。
ふむ、とすると、『能力』なんて幻とかなんとかうそぶきながら、それを飯のタネにしてきたのは、やはり母さん、あなたのいた業界じゃないか。」(本文より)
執筆に伴走した、磯野真穂さん(人類学者)も言葉を寄せる。
📗 働くということ
他者と働くということは、一体どういうことか? なぜわたしたちは「能力」が足りないのではと煽られ、自己責任感を抱かされるのか? 著者は大学院で教育社会学を専攻し、「敵情視察」のため外資系コンサルティングファーム勤務を経て、現在は独立し、企業などの「組織開発」を支援中。本書は教育社会学の知見をもとに、著者が経験した現場でのエピソードをちりばめながら、わたしたちに生きづらさをもたらす、人を「選び」「選ばれる」能力主義に疑問を呈す。そこから人と人との関係を捉え直す新たな組織論の地平が見えてくる一冊。
「著者は企業コンサルタントでありながら(!)能力と選抜を否定する。本書は働く人の不安につけこんで個人のスキルアップを謳う凡百のビジネス本とは一線を画する」――村上靖彦氏(大阪大学大学院教授、『ケアとは何か』『客観性の落とし穴』著者)推薦!
◆目次◆
序章 「選ばれたい」の興りと違和感
第一章 「選ぶ」「選ばれる」の実相――「能力」の急所
第二章 「関係性」の勘所――働くとはどういうことか
第三章 実践のモメント
終章 「選ばれし者」の幕切れへ――労働、教育、社会
これらの本および著者である勅使河原真衣さんはフィールドは「企業」「就労の場」で、テーマは「働く」ということですが、「能力主義」を問い直す試みを、この本を皮切りに続けていらっしゃいます。教育社会学を学んだ上で、組織開発を仕事にしてきたという経歴の面白さと説得力。新著の『職場で傷つく~リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』もとても示唆に富んでおもしろいです。
一応読んでいることを前提にして会は進行しますが、読んでいなくても参加OK!
関心ある方、気軽にご参加ください。
もし誰も来なくてもみどりとなおさんが語り合っています(笑)
■個人情報の取り扱いについて
お申し込み時にご登録いただいた個人情報は、企画者が次の目的の範囲で必要な限りにおいて利用するものとします。
・本イベントの事前事後の連絡
・イベント・プログラム等の告知、その他の宣伝活動
ご提供頂いた個人情報の取り扱いに関するご要望・お問い合わせは、School Voice Project 事務局( info@school-voice-pj.org )までお願いします。