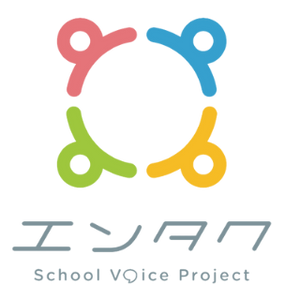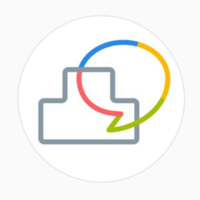埼玉県公立高校教員で、NPO法人School Voice Project(SVP)の理事でもある、@たーぼう(逸見峻介) さんの本が出ました!
埼玉県立新座高校では、2023年4月に校務分掌の「生徒指導部」を「生徒支援部」に改称し、学校を「生徒を『支援』する組織」にするための改革が行われました。
生徒指導部長(当時)としてその中心となったが逸見さんです。
生徒指導提要も改訂され、生徒指導の考え方が変わっていく中で、逸見さんがどんな考え・思いでこの取り組みを行ったのか、具体的にはどんなふうに進めていったのか、がわかる本です。ぬくもりのある、民主的で対話的な、風通しのいい学校にしていくために、“分掌からできること”を一緒に考えませんか??
本を読んでから来てくださるとベストではありますが、未読でもご参加いただけます◎
当日は著者の逸見さんも参加の予定です。ぜひ気軽にご参加ください。
◎今回みんなで読む本『生徒指導部から生徒支援部へ』
はじめに
第1章 生徒「支援」とは?
・生徒「支援」とは?
・「指導」と「支援」
・「生徒支援部」に名前を変える意味
・なぜ「生徒支援」が必要なのか
・生徒指導提要の改訂
・生徒指導の現在地は――陥りがちな5つの誤解
・学校はこうあってほしい、「3つの願い」
第2章 生徒を「支援」する取り組み ~埼玉県立新座高校の実践~
・実践を始める前の学校の印象
・具体的な取り組みの始まり――見直しの4つの観点設定
・民主的で対話的な組織へ
・ぬくもりのある組織
・多様性と人権の尊重
・働き方改革
・残された課題
第3章 生徒を「支援」する教員とは
・「説諭」と「問い」を活用する生徒支援
・ファシリテーターとしての教員
・アセスメントを用いた「ポジティブ行動支援」
・対話をベースにしつつも、指導のラインは譲らない
・求められるのは「探究のマインド」
・生徒の「ウェルビーイング」を目指す
コラム:情報収集のヒント
第4章 生徒を「支援」する分掌とは
・民主的で対話的な組織
・常に組織体制を見直していく姿勢
・生徒の問題行動を「社会モデル」で考える
・心理的安全性がある組織
・教員のウェルビーイングを目指す
コラム:SNSを用いた情報収集
終わりに
参考文献一覧