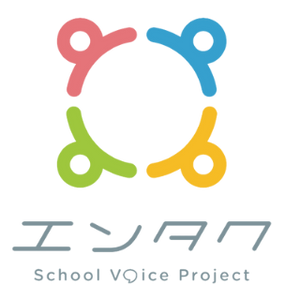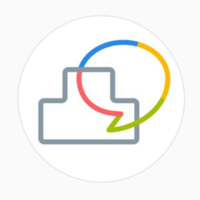星野俊樹さんと考える
「ジェンダー教育、どこから手をつける?」
ジェンダー平等、包括的性教育、フェミニズムを教育に取り入れる必要性は、ますます広く認識されるようになりました。しかし「何から始めればいいのか分からない」「敷居が高い」「自分が語っていいのか不安」という声が多いのも現実です。この講座では、理論と実践をつなぎ、自分の教室や職場に引き寄せて考えられる視点を育みます。
日程・時間
※全3回・オンライン
第1回 7月23日(水)20:00–21:30
第2回 7月30日(水)20:00–21:30
第3回 8月13日(水)20:00–21:30
ナビゲーター
星野俊樹さん
1977年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、雑誌編集者を経て小学校教師に転身。公立小学校での勤務を経て、京都大学大学院教育学研究科に進学し、修士課程を修了。その後、私立小学校に着任し、教員としてのキャリアを重ねる。教員歴は20 年。現場では、ジェンダー平等を目指す教育実践に取り組んできた。2025 年3月末に退職し、現在は執筆や講演などを通じて活動の幅を広げている。6月に時事通信社から単著『とびこえる教室: フェミニズムと出会った僕が子どもたちと考えた「ふつう」』が発刊されたばかり。
https://amzn.to/3Tdt5Jv
第1回 「ジェンダー教育に取り組む前に持っておきたい基礎知識」 ← 今回!
「男だから」「女だから」という決めつけは、どのように作られ、どのように教育現場に影響しているのか。神経学的性差別(ニューロセクシズム)、家父長制、有害な男性性、ジェンダーステレオタイプ、脳の可塑性といった視点から、性差の「根拠」を問い直します。
▼主なトピック
・LGBTQとSOGIEの違い
・神経学的性差別と脳の可塑性
・本質主義と構築主義
・家父長制
・有害な男性性
・ステレオタイプ脅威
・包括的性教育の意義
▼ゴール
・科学的・社会的に性差を理解する
・無意識の偏見に気づく
・ジェンダー教育の必要性を他者に説明できる
第2回「教室をフェミニズムの視点でまなざす」
「自分らしさを大切にする」という実践、個人(点)をエンパワーする大切なものです。しかし、この実践だけでは、教室の構造的不平等は変わりません。この回では、教室に潜む権力関係・ジェンダー秩序を、子どもどうしの関係性(線)として捉える視点を学びます。私の実際の実践報告を通じてその視点について学び、考えましょう。
▼主なトピック
・「男子の権力」
・「男らしい文化」の再生産
・「受容的なスタンス」の限界
・教室の中で再現される性別役割分担
・柔らかい声をエンパワーする実践
▼ゴール
・教室を批判的に観察する目を育む
・教師自身の権力性に気づく
・小さな実践のヒントを持ち帰る
第3回「性別にとらわれない視点と、あえて性別にこだわる視点の間で」
(ディスカッション主体の授業となります)
「性別にとらわれない」ことは大切ですが、それだけでは性差別を看過し、温存してしまう危うさがあります。この回では、性別を「見えないもの」として扱うリスクと、「あえて性別にこだわる」意義を行き来する視点を学びます。支援対象の性別の偏りやヒドゥンカリキュラムを題材に、二つの視点を往復するしなやかさを考えます。
▼主なトピック
・性別二元論と異性愛規範の問い直し
・ADHD支援の性別偏りと診断基準の歴史
・ケア労働のジェンダー分業をめぐる構造的問題
・性別をめぐる免責装置としての語り
▼ゴール
・二つの視点を柔軟に行き来できる
・「見えにくい偏り」に気づく
・状況に応じた実践を考えられる